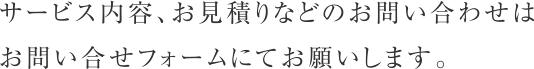2016.10.10
診察室「おもてなし」磨く 医学生、英語で外国人付き添い 五輪向け実力底上げ

2016/10/9付 日本経済新聞
首都圏を中心とした医学生約300人が勉強会やボランティアを通じ、英語での外国人患者への対応力を磨いている。異国では症状を伝えるだけでも容易でないが、コミュニケーションまで目配りした医学部の講義は少ない。2020年に東京五輪・パラリンピックを控え、今後も訪日客は増えそう。将来、診察を担うこうした医師の卵たちの実力底上げが不可欠だ。
「横になってください」「気持ち悪くないですか?」。都内の総合病院の一室で、大腸の内視鏡検査を受ける外国人患者に医学生が英語で話しかけた。付き添いボランティアの一場面だ。技術の進歩で体への負担は軽減したとはいえ、母国外で機器を使った検査を受ける不安は小さくない。
有志300人が活動
医学生は外国人患者のサポートのため昨年7月に発足した「チームメディックス」のメンバーだ。当初は日本大学や慶応大学などの医学部の有志約90人でスタートし、現在は約300人に膨らんだ。
付き添いボランティアなど現場研修には国立国際医療研究センター病院(東京・新宿)やがん研有明病院(同・江東)など、外国人が多い病院が協力。医学生は医師免許を持っていないため直接診察はできないが、話しかけることで患者の不安を和らげる。
外国人にとって、病院にたどり着いてからも不慣れなことは多い。例えば問診票の記載や診療後の会計。医学生は症状に耳を傾け、日本語による問診票代筆などにも取り組む。
勉強会は月1回開いている。外国人は受診時に発熱や疲労を医師に訴えても、それに伴う細かな体の状態までは伝わりづらい。このため勉強会では、日本の大学で医学を教える外国人医師らを講師として、適切な治療に結びつけるためのコミュニケーションの方法論を学んでいる。
例えば発熱の場合はまず「最近、海外旅行をしましたか」と質問。「いいえ」なら「病院にかかっていますか」などと場合分けしていき、症状が感染性の病気によるものか、炎症によるものかなどを突き止めていく。医療費の支払いでトラブルが起きないよう、日本の医療保険制度についても説明できるようにする。
大学医学部は英語をカリキュラムに組み込んでいるが、外国人患者とのコミュニケーションを想定した授業は少ない。日大で医学英語を教える押味貴之助教は「学生は外国人患者と接する機会は少ないものの、将来に備えて学ぶ必要がある」と指摘する。米国などへの留学時にも「話す力」「聴く力」が求められ、宗教や異文化への理解も必要となる。…(省略)
20年の東京五輪・パラリンピックに向け、外国語対応のボランティアの育成は急務。医療サービスの充実も「おもてなし」の一つになる。医師の卵たちの試みは、日本のソフトパワーの強化につながるだろうか。